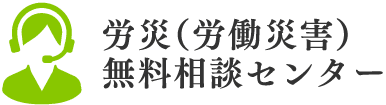労災保険の補償には、複数の種類があります。
その中のひとつが、障害(補償)給付です。
これは、労災事故で負った怪我や病気の後遺障害に対する給付金です。
今回は、この給付について、申請の流れや給付金額など詳しく解説します。
労災の障害(補償)給付とは
労災による傷病が治ゆした時、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付金のこと。
障害(補償)年金(一時金)、障害特別支給金、障害特別年金(一時金)の3種から成る。
※治ゆとは、傷病が完治した状態だけを指さず、一般的な医療を施してもその効果が期待できなくなった状態を指す(症状固定)。
労災の後遺障害については、症状の程度による等級が定められています。
障害(補償)給付は、この等級に応じて、年金型と一時金型の2種類に分かれています。
・等級第1級〜7級・・・年金
・等級第8級〜14級・・・一時金
一時金であれば、受けられる給付は1度きりです。
しかし、年金であれば、労災被害にあった労働者は一生涯給付金を受け取り続けることが可能です。
ただし、年金を受け取っていても、その後の障害等級に変更が起きた時には、補償内容および金額に変更が生じる可能性があります。
またこの年金は、給付金の支給要件を満たした月の次の月分から支給が始まります。これは毎月振り込まれるわけではなく、前2ヶ月分をまとめた金額が各偶数月に支払われます。
労災の障害(補償)給付 申請までの流れ
労災で補償を受けるには、申請手続きが必要です。ここでは、障害(補償)給付の申請手続気を行うまでの流れを見ていきましょう。
申請の流れ
前述の通り、この給付を受けるためには、労災で負った傷病が治ゆしたと診断されなければなりません。
症状が治ゆするまでには、医療機関での治療が必要です。そして、この治療にかかる費用を補償するのが、労災保険の療養(補償)給付です。
この療養(補償)給付を受けながら療養を続け、傷病が治ゆした後に申請できるのが、障害(補償)給付です。この流れをまとめると、次のようになります。
2.療養(補償)給付の申請・受給
3.療養を経て傷病が治ゆ(症状固定)
4.障害(補償)給付の申請・受給
傷病が治ゆすると、療養(補償)給付は打ち切りとなります。障害(補償)給付との併給は許されていません。
また、これらの補償とは別に、会社を休むこととなった場合には休業(補償)給付、療養を始めてから1年6ヶ月経っても傷病が治ゆせず、その状態が規定の傷病等級に当てはまる場合には傷病(補償)年金を受け取ることも可能です。
各給付には要件が設定されているので、自分の状態がどの給付金の補償対象となるのか、よく確認するようにしましょう。
申請手続き
具体的な申請手続きについても確認しておきましょう。
障害(補償)給付の申請は、請求書の様式第10号または様式第16号の7を用い、次の流れで行います。
2.請求書を作成する
3.事業主に証明をもらう
4.事業所を管轄する労働基準監督署に書類を提出する
5.労働基準監督署の審査
6.支給・不支給の決定
労災保険の請求書は種類が多く、使うべき様式は給付金や労災の種類ごとに決まっています。異なる請求書では申請受付はされないので、間違いのないよう注意してください。
障害(補償)給付の給付金額
次に、給付金額についてご説明します。
障害(補償)給付の給付金額は、該当する障害等級によって異なります。ここでは厚生労働省の資料をもとに、各等級における支給金額を表で見ていきます。
【障害(補償)年金の支給金額】
| 等級 | 障害(補償)年金 (給付基礎日額で計算) |
障害特別支給金(一時金) | 障害特別年金 (算定基礎日額で計算) |
|
| 第1級 | 313日分 | 342万円 | 313日分 | |
| 第2級 | 277日分 | 320万円 | 277日分 | |
| 第3級 | 245日分 | 300万円 | 245日分 | |
| 第4級 | 213日分 | 264万円 | 213日分 | |
| 第5級 | 184日分 | 225万円 | 184日分 | |
| 第6級 | 156日分 | 192万円 | 156日分 | |
| 第7級 | 131日分 | 159万円 | 131日分 |
【障害(補償)一時金の支給金額】
| 等級 | 障害(補償)一時金 (給付基礎日額で計算) |
障害特別支給金(一時金) | 障害特別一時金 (算定基礎日額で計算) |
| 第8級 | 503日分 | 65万円 | 503日分 |
| 第9級 | 391日分 | 50万円 | 391日分 |
| 第10級 | 302日分 | 39万円 | 302日分 |
| 第11級 | 223日分 | 29万円 | 223日分 |
| 第12級 | 156日分 | 20万円 | 156日分 |
| 第13級 | 101日分 | 14万円 | 101日分 |
| 第14級 | 56日分 | 8万円 | 56日分 |
(厚生労働省『労災保険 障害(補償)等給付の請求手続』より)
ここで注目したいのが、給付基礎日額と算定基礎日額というワードです。
これらの意味も確認しておきましょう。
労働基準法における平均賃金にあたる金額のこと。
労災事故発生日または医師による診断確定日の直前3ヶ月の間に、被災労働者が受け取った賃金の総額を歴日数で割った額(つまり1日あたりの賃金額)。
ただし、ボーナスや臨時的な賃金は含まない。
労災事故発生日または医師による診断確定日以前の1年の間に、被災労働者が受け取った特別給与の総額を365で割った額。ここで言う特別給与とは、3ヶ月以上の期間ごとに受け取るボーナスなどの賃金のこと(臨時的な賃金は除外)。
ただし、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の2割以上になる場合には、給付基礎年額の2割にあたる額を算定基礎日額とする。
限度額は150万円。
上記の通り、給付基礎日額と算定基礎日額は言葉は似ていますが、内容は異なります。給付金額を試算する際には、これらを混同することのないよう注意してください。
障害補償給付の申請に診断書は必要?
結論から述べると、障害(補償)給付の申請には、診断書が必要です。必ず、担当の医師や歯科医師に診断書を書いてもらい、それを給付金の請求書類に添付した上で、労働基準監督署へ提出してください。
また、場合によっては診断書だけでなく、レントゲン写真などの資料の添付が求められることもあります。
この時かかった診断書作成料は、療養(補償)給付の補償対象となります。「療養給付たる療養の費用請求書」第7号または第16号の5を作成し、労働基準監督署へ提出すれば、診断書作成料の補償を受けられます。ただし、その上限は4,000円です。
また、この料金は被災労働者自身が一度立て替え、その後労災保険へ請求して返金を受ける形になります。作成料の支払い後は速やかに手続きを行い、請求を失念しないよう気をつけましょう。
(労災申請に必要な診断書については、こちらで詳しく解説しています。「労災申請に診断書は必要?費用負担についても解説」)
まとめ
労災保険の障害(補償)給付は、労災による怪我や病気が治ゆした後、一定の障害が残った場合に支給される給付金です。給付の形は年金と一時金の2種に分けられ、該当する障害等級によってその支給額は異なります。
支給額は、給付基礎日額と算定基礎日額が基準となるので、それぞれどのようなものなのか確認しておきましょう。
また、障害(補償)給付を受ける際には療養(補償)給付は打ち切りになること、請求時には医師の診断書が必要になることも覚えておいてください。
労災については、事業主との間でトラブルが起きたり労災隠しに巻き込まれたりする例も少なくはありません。
労災についての困り事は、1人で抱え込まず、労災問題の実績豊富な弁護士にご相談ください。弁護士は法律の専門家として、労災問題を解決へと導きます。
「弁護士への相談はハードルが高い」と感じる方は、まずは無料相談をご活用ください。