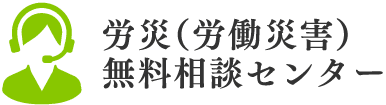被災労働者が労災保険からの給付金を受け取るためには、所轄の労働基準監督署に所定の様式で申請を行う必要があります。申請後、労働基準監督署による調査を経て労災と認定されると、労働者は補償を受けることができます。
では、労災保険から給付金を受け取るためには、どのような手続きをしなければならないのでしょうか。
今回は、労災申請の手続きの流れと注意点、また労災申請を行わないことで受けるデメリットなどについて、わかりやすく解説していきます。
労災保険の申請手続きの流れ
労災保険の申請手続きは、以下の流れで進めていきます。
- 労災発生の旨を会社へ報告する
- 医療機関を受診する
- 労災保険の申請に必要な書類を用意する
- 労働基準監督署へ書類を提出する
- 労働基準監督署による調査が行われる
- 労災認定・不認定の決定と給付金の支給が行われる
ここでは、上記の各手順について、詳しくみていきましょう。
1.労災発生の旨を会社へ報告する
労働災害(労災)が発生したときには、まず会社へその旨を報告する必要があります。なぜなら、業務上の災害について、会社には労働基準監督署に死傷病報告を提出する義務があるためです。
また、労災保険の給付請求は原則として労働者自身が行うものであり、会社が代行する義務はありません。しかし、会社の協力が必要な手続きも多いため、迅速な報告は重要です。
被災労働者本人が労災保険の補償をスムーズに受けるためにも、労災に遭った場合には速やかに会社に連絡し、状況や原因などを具体的に説明しましょう。本人による連絡が困難な場合には、居合わせた同僚や上司などに連絡を頼むと良いでしょう。
またこの連絡では、必ず「労災である」ことを明確に伝えることが大切です。
2.医療機関を受診する
労災により傷病を負った場合には、すぐに医療機関を受診し、必要な治療を受けます。
このとき、労災保険指定医療機関(労災指定病院)を受診するか、それ以外の病院を受診するかで、治療費等の支払い方は変わります。
労災保険指定医療機関を受診した場合、労働者は医療費を支払う必要がありません。治療や薬は現物支給という形で提供され、その代金は後から労災保険によって支払われます。
一方、指定されていない医療機関を受診した場合、労働者はかかった医療費を全額立て替えなければなりません。健康保険は使えないので、このときの支払いは10割となります。
立て替えた医療費は後日労災保険から返金されますが、立て替えが困難な場合には、労災保険指定医療機関を受診した方が良いでしょう。
また、受診するすべての医療機関において治療を受ける際には、窓口で「労災による傷病である」ことを明確に伝え、健康保険証は使わないようにしてください。
3.労災保険の申請に必要な書類を用意する
労災保険の給付請求は原則として被災労働者本人が行う手続きです。ただし、会社が補助的に手続きを進める場合もあります。
その場合には、労災保険の申請に必要な書類の用意から始めましょう。
労災保険には複数の給付金が用意されており、「どの給付金を申請するか」また「業務災害か通勤災害か」によって、作成すべき請求書や添付すべき資料は異なります。
例えば、業務災害によるケガの医療費(労災指定病院を受診)を請求する場合には、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を使用します。
一方、通勤災害によるケガで労災指定以外の病院を受診した場合には、「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」を使用します。
請求書の種類は非常に多いので、様式を間違えないよう気をつけましょう。
各請求書については、厚生労働省『主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)』からダウンロードが可能です。
また、請求書の作成にあたっては、事業主や病院の証明が必要になります。もし事業主の協力を得られない場合には、証明欄が空欄でも労働基準監督署に事情を説明すれば申請を受け付けてもらえる可能性があります。
4.労働基準監督署へ書類を提出する
請求書の作成と添付資料の用意が整ったら、労働基準監督署へ書類を提出します。このときの提出先は、原則として、事業所を管轄する労働基準監督署の窓口です。
請求書の事業主証明欄を記入してもらえなかった場合には、その旨を窓口の担当者に伝えましょう。
ただし、「療養補償給付たる療養の給付」(様式第5号)を提出する場合に限り、例外があります。
労災保険指定医療機関で受診したときは、その医療機関が労働基準監督署への提出を代行してくれることがあります。
提出先を間違えないよう注意しましょう。
5.労働基準監督署による調査が行われる
書類提出後は、労働基準監督署による調査が行われます。この調査に基づき、労働基準監督署長が労災保険給付の可否を決定します。
労災がケガである場合、業務との因果関係が比較的はっきりしているため、調査は短期間で終了します。一方、うつ病などの精神障害や脳・心臓疾患などの場合は、業務との因果関係を客観的に判断する必要があるため、調査には時間がかかる傾向があります。
6.労災認定・不認定の決定と給付金の支給が行われる
調査が終わると、労働基準監督署長により、労災認定・不認定の判断が行われます。労災が認定された場合には、労災保険からの給付金の支給が開始されます。
この結果は、「労災保険給付支給決定通知書」などの書面やハガキで通知されることが一般的ですので、必ず確認しておきましょう。
一方で、不認定となった場合は給付金を受け取ることができませんが、その決定に不服がある場合には不服申立てを行うことが可能です。
労災の不服申立て制度とは?
労働基準監督署長の決定に不服がある場合、まず審査請求を行うことができます。さらに、その決定にも不服がある場合には再審査請求、最終的には取消訴訟を提起することが可能です。
【審査請求】
- 請求先:都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官
- 期日:労災認定・不認定の決定を知った日の翌日から3カ月以内
【再審査請求】
- 請求先:労働保険審査会
- 期日:審査官から決定書の送付を受けた翌日から2カ月以内または審査請求後3カ月が経過しても決定がない場合
【取消訴訟】
- 請求先:地方裁判所
- 期日:審査会の裁決を知った日の翌日から3カ月以内 または 再審査請求後3カ月が経過しても裁決がない場合
これらの手続きでは、段階によって請求先や請求期限が異なるため、注意が必要です。
労災申請の手続きは誰が行う?
労災保険について定めた労災保険法第12条の第2項には、以下の旨が記載されています。
保険給付は、規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
(参考:e-Gov法令検索『労災保険法』)
法律では、労災申請の手続きは労災に遭った労働者本人やその遺族、葬祭を行う者が行うことが原則です。
しかし現実には、労働者に代わって会社が労災申請の手続きを補助的に行うことがあり、労働者自身が全ての手続きを行うケースはあまりありません。これは、アルバイトやパート、日雇い労働者であっても同様です(派遣労働者の場合は派遣元の会社が対応)。
ただし、会社によっては、代理手続きを行わないケースもあるようです。会社が手続きをしてくれない場合には、労働者自身が手続きを行う必要があります。
【関連記事】労災を申請する流れを徹底解説!病院受診から給付まで
労災申請の手続きを行う際の注意点
労災申請の手続きには、知っておくべき注意点がいくつかあります。ここでは特に重要なポイントを4つご紹介します。
労災申請から支給までにはある程度の時間がかかる
労災を申請してから給付金が支給されるまでには時間がかかります。給付金ごとの目安は、以下のとおりです。
- 療養(補償)給付:おおむね1カ月
- 休業(補償)給付:おおむね1カ月
- 遺族(補償)給付:おおむね4カ月
- 障害(補償)給付:おおむね4カ月
(参考:厚生労働省『労災保険請求のためのガイドブック』)
ただし、申請から支給までにかかる実際の時間は、ケースバイケースです。上記はあくまで目安であり、それよりも長い時間がかかるケースも少なくはありません。
特に、精神疾患や脳・心臓疾患に関する事案(いわゆる過労自殺や過労死を含む)の場合、労災認定の判断にはより慎重な調査が必要になります。そのため、申請から支給までの時間は長くなる傾向があります。こうした場合は、半年から1年以上かかることもあります。
会社が手続きに協力してくれなくても申請はできる
会社によっては、労働者の代理で労災申請の手続きを行わないところもあります。中には、証明欄の記入などといった手続きへの協力さえ拒む会社もあるようです。
このような場合でも、被災労働者は労災申請を諦める必要はありません。
既にご紹介したとおり、労災申請の手続きは、被災労働者自身が行うことが法的に認められています。会社の協力を受けられず証明欄が空白の場合でも、書類提出時にその旨を労働基準監督署の窓口で伝えれば、申請は受け付けてもらえます。
会社が労災申請を拒否する場合、その背景には「労災隠し」の意図があるかもしれません。
労災隠しとは、労災が発生しているにも関わらず、労働基準監督署への報告をしなかったり労働者の労災申請をさせなかったりなど、労災発生の事実を隠そうとする行為です。労災が発生すると、会社には保険料の増額などの経済的不利益が生じることがあるため、労災を隠したがる事業主がいると考えられます。
ただし、労災隠しは労働安全衛生法(職場の安全や健康を守るための法律)に違反する行為であり、刑事罰の対象となります。会社が労災隠しを行おうとしても、労働者がそれに従う必要はありません。
会社に協力を得られない場合や会社が労災申請を認めない場合でも、労働者は自分で手続きを行うようにしましょう。
労災申請には時効が存在する
労災申請には、給付金ごとに定められた時効があります。時効までに申請を行わなければ、給付金の請求権は消失してしまいます。
給付金ごとの時効は以下のとおりです。
- 療養(補償)給付:療養の費用を支出した日の翌日から2年
- 休業(補償)給付:賃金を受けなかった日の翌日から2年
- 遺族(補償)給付:労働者が亡くなった日の翌日から5年
- 葬祭料(葬祭給付):労働者が亡くなった日の翌日から2年
- 傷病(補償)年金:障害が確定した日の翌日から5年
- 障害(補償)給付:障害が確定した日の翌日から5年
- 介護(補償)給付:介護を受けた月の翌月1日から2年
(参考:厚生労働省『労災保険に関するQ&A』)
労災申請においては、時効を意識しながら、なるべく早めに手続きを行うことが重要です。
労災保険では慰謝料は補償されない
労災保険では、労災によるあらゆる傷病に対する補償(給付金)が用意されています。しかし、精神的苦痛に対する慰謝料や、失った収入に対する補償など、民事上の損害賠償にあたるものは含まれていません。
慰謝料を受け取るためには、会社または第三者に対し、損害賠償を請求する必要があります。ただし、損害賠償を請求できるのは、会社や第三者に落ち度があり、労働者に損害を与えたと認められる場合に限られます。
会社や相手に責任があるかどうかの判断や、損害賠償を請求するための手続きは専門的で難しいことが多いため、検討する場合は弁護士に相談するのが安心です。
労災申請の手続きを行わない場合のデメリット
「会社が労災申請に協力してくれない」「自分で手続きを行うのが面倒だ」などの理由で労災申請の手続きを行わないのは、おすすめできません。なぜなら、労災申請を行わないことで、被災労働者は以下のデメリットを被ることになるためです。
- 治療費を全額自分で支払わなければならない
- 休業や後遺障害などに対する補償を受けられない
労災による傷病であるにもかかわらず労災申請を行わない場合、健康保険は原則として適用されないため、治療費を全額自己負担する必要が生じることがあります。これは被災労働者にとって、大きな経済的負担となるでしょう。
また、労災申請を行わなければ、休業や後遺障害に対する補償も受けられません。働けなくなったり障害が残ったりして収入が減ったときに、何の補償も受けられないとなると、生活は苦しくなってしまう可能性があります。
このような事態を避けるためにも、労災に遭ったときには、必ず労災申請を行うようにしましょう。
労災申請の手続きはあとからできる?
労災による傷病の治療で誤って健康保険を使用した場合でも、あとから労災申請を行い、労災保険へ切り替えることが可能です。
その際は、まず受診した医療機関に「労災保険への切り替えを希望する」旨を連絡してください。
医療機関での対応が難しい場合は、加入している健康保険組合に連絡し、健康保険で支払った医療費を返納したうえで、通常どおり労災申請の手続きを行います。
詳しい手続きについては、厚生労働省の資料『健康保険から労災保険の切替手続きについて』をご確認ください。
まとめ
労災に遭ったときには、生活を安定させ不安を減らすためにも、労災保険による補償をしっかり受けることが大切です。会社が代理手続きをしない場合でも、申請をあきらめるのではなく、被災労働者自身で手続きを行うことが可能です。
労災無料相談センターでは、労災保険の申請や損害賠償請求に関するご相談を受け付けています。手続きに不安がある方、労災隠しの被害に遭った方、また損害賠償請求を検討する方は、ぜひご相談ください。
実績豊富な弁護士が手続きをサポートし、不安や負担を軽減します。