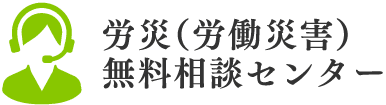労災によって傷病を負った労働者の中には、在職中は労災申請を行う余裕がなく、退職後に申請を検討し始めるという人もいるでしょう。
労災申請は、退職後であっても一定の期限内であれば行うことができます。「もう退職したから」と、申請を諦める必要はありません。
そこで今回は、退職後の労災申請の詳細や労働者が取るべき対応、申請期限など知っておくべきポイントについて、わかりやすく解説します。
労災に遭った方はもちろん、万が一の労災に備えたい方も、参考にお役立てください。
労災とは
「労災」とは、「労働災害」を略した言葉で、業務上の原因や通勤によって労働者が負った傷病のことを指します。業務中に負った傷病は「業務災害」、通勤中に負った傷病は「通勤災害」として扱われます。
また、労災が発生した場合に、被災労働者に対し給付金等による補償を行う公的保険制度を「労災保険(労働者災害補償保険)」と呼びます。
労災保険の主な給付金は以下のとおりです。
- 療養補償給付・療養給付
- 休業補償給付・休業給付
- 休業(補償)給付
- 傷病(補償)年金
- 障害(補償)給付
- 介護(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料(葬祭給付)
上記の給付金は、労災認定を受け、それぞれの要件を満たした被災労働者に対し支給されます。
労災保険は原則としてすべての労働者(パート・アルバイト含む)を対象にした保険で、従業員を雇用する事業主は、必ずその従業員を労災保険に加入させなければなりません。保険料も、全額事業主が支払うことになります。
保険利用にあたっては、労働者自身の過失は問われず、重過失がない限り、給付が減額されることは基本的にありません。
ただし、労災保険の給付を受けるためには、所定の申請手続きが必要になります。
退職後の労災申請は可能
労災によってケガをしたり病気になったりした被災労働者の中には、在職中に労災申請の手続きをする余裕がなかったという方もいるでしょう。
在職中に労災申請の手続きができていなくても、問題はありません。労災申請は、退職後に行うことも認められています(※一定の時効制限あり)。
労災保険については労働者災害補償保険法で定められていますが、ここで注目したいのが以下の条項です。
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
(引用:e-Gov法令検索『労働者災害補償保険法 第12条の5』)
この条文は、退職後であっても労災保険の申請・給付を受ける権利を失わないことを意味しています。
原則、労災保険の申請手続きは、被災労働者本人が行うことになっています。しかし実際には、会社が代理で手続きを進めてくれるケースが多いようです。
ただし、会社が手続きをしてくれないときには、忘れずに労働者本人が書類提出などの手続きを行うようにしましょう。
また、労災申請の書類に、労災時に所属していた会社による証明欄がある点には注意が必要です。退職後の場合、勤めていた会社に証明欄の記入を依頼するのが困難だという場合もあるでしょう。
この証明欄の記入について勤めていた会社に協力を得られない場合でも、申請自体は受け付けられる可能性があります。その際は、労働基準監督署に事情を説明し、必要に応じて補足資料の提出を求められることがあります。
会社からの退職勧奨に従う必要はない
労災によってケガや病気を負った労働者が、負担を軽減するため、自ら退職することには法的問題はありません。
しかし、労災によって休業中・休業後の労働者を会社が解雇することは、労働基準法の以下の条項で禁止されています。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
(e-Gov法令検索『労働基準法 第19条』)
この法律による解雇制限があるからこそ、解雇ではなく、あえて退職勧奨を被災労働者に行う会社が存在します。
退職勧奨とは、会社側が労働者自身の意思による退職を促すことです。退職勧奨による退職は、あくまで労働者の自主退職であるため、解雇制限には抵触しない可能性があります。
しかし、上司などから退職勧奨を受けたとしても、被災労働者はそれを拒否することができます。退職の意思がないのであれば、「辞めません」と、明確に断りましょう。
ちなみに、退職勧奨として実質的に退職を強要することは違法とされる場合があります。従って、被災労働者が退職勧奨を拒否すれば、会社側はそれ以上の対応を一方的に押しつけることは望ましくありません。
【ケース別】自分で労災申請を行う方法
ここからは、被災労働者が自分で労災申請(療養補償給付・療養給付)を行う方法をご紹介します。
受診する病院によって手続きは少し異なるので、しっかり確認しておきましょう。
労災指定病院を受診した場合
病院には、労災指定病院と、そうでない医療機関があります。労災の療養にあたって労災指定病院を受診した場合、窓口で労災である旨を伝えれば、被災労働者は原則として自己負担なく治療や薬を提供してもらうことが可能です。
労災申請(療養補償給付・療養給付の請求)を行う際には、請求書を作成する必要があります。このとき使用する請求書は以下のとおりです。
- 業務災害の場合:療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 (様式第5号)
- 通勤災害の場合:療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
これらの書類は、厚生労働省のWebサイト内『主要様式ダウンロードコーナー』からダウンロードできます。
請求書を作成したら、会社に証明をもらってから、受診した労災指定病院の窓口に提出します。その後、労働基準監督署の調査を経て、労災が認定されるかどうかが判断されます。
労災指定以外の病院を受診した場合
労災の療養にあたって、労災指定以外の病院を受診する場合も、窓口で労災である旨を伝える必要があります。この場合、療養にかかった費用は、被災労働者が一旦その全額を立て替えることになります。
その後の労災申請(療養補償給付・療養給付の請求)では、以下の請求書を用います。
- 業務災害の場合:療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書 (様式第7号)
- 通勤災害の場合:療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
これらの書類は、厚生労働省のWebサイト内『主要様式ダウンロードコーナー』からダウンロードできます。
請求書を作成したら、会社と受診した病院に証明をもらい、所属する事業所を管轄する労働基準監督署の窓口へ提出します。その後、労働基準監督署の調査を経て、労災認定・不認定の判断が行われ、労災が認定されれば、指定口座に立て替えた分の療養費が振り込まれます。
健康保険を使ってしまった場合
労災によるケガや病気の治療には、健康保険は原則として適用されません。健康保険では、業務上の傷病は労災保険の対象とされるため、原則として補償の対象外です。
労災であるにもかかわらず医療機関で健康保険を使用してしまった場合は、後から労災保険に切り替える手続きが必要になることがあります。
健康保険から労災保険への切り替えは、次のような流れで行われます。
- 受診した医療機関に連絡し、労災への切り替えが可能かを確認する。切り替え可能な場合は、そのまま労災申請へ進む
- 医療機関で切り替えができない場合は、加入している健康保険組合に連絡し、切り替えの可否を相談する
- 健康保険組合からの指示に従い、健康保険で支払った医療費を返納するよう求められることがある
- 返納後、労災保険への申請手続きを行う
詳しい手続きについては、厚生労働省 滋賀労働局の資料『健康保険から労災保険の切替手続きについて』もご確認ください。
【関連記事】労災を申請する流れを徹底解説!病院受診から給付まで
労災申請の時効
労災申請は退職後でも原則として可能です。
ただし、請求には給付の種類ごとに時効があるため、注意が必要です。
労災給付金の種類ごとの時効は、以下のとおりです。
- 療養(補償)給付:療養の費用を支出した日の翌日から起算して2年
- 休業(補償)給付:賃金の支払いを受けなかった日の翌日から2年
- 傷病(補償)年金:年金の支給要件を満たした日の翌日から5年
- 障害(補償)給付:傷病が治ゆ(症状固定)した日の翌日から5年
- 介護(補償)給付:介護を受けた月の翌月1日から2年
- 遺族(補償)給付:労働者が亡くなった日の翌日から5年
- 葬祭料(葬祭給付):労働者が亡くなった日の翌日から2年
時効を過ぎると、給付金の請求権は消滅します。補償を受けるためにも、労災申請の手続きは早めに行うことをおすすめします。
【関連記事】労災には2年と5年の時効がありますので、お早めにご相談を!
労災が原因で障害が残りそうな場合の手続き
労災による傷病が治ゆしたとき、身体に一定の障害が残った場合には、被災労働者は労災保険の障害(補償)給付を受けることができます。
障害(補償)給付では、被災労働者の身体に残った障害が規定の障害等級の何級に該当するかによって、給付金の種類や支給方法、金額が異なります。
障害等級ごとの給付金の種類は以下のとおりです。
- 障害等級第1級〜7級:障害(補償)年金(定期的に支給される年金)、障害特別支給金(上乗せの一時金)、障害特別年金(上乗せの年金)
- 障害等級第8級〜14級:障害(補償)一時金(まとめて支給される一時金)、障害特別支給金(上乗せの一時金)、障害特別一時金(上乗せの一時金)
障害(補償)給付では、等級が重いほど支給される給付金額が高くなるため、「適切な等級認定を受けられるか」が重要なポイントになります。そのためには、労災問題を扱う弁護士にアドバイスを受けることも有効です。
会社への損害賠償請求が可能なケース
会社に法的責任がある場合、被災労働者は損害賠償を請求できます。
労災発生にあたっての会社の法的責任として挙げられる代表的なものは、「安全配慮義務違反(労働契約法第5条)」と「使用者責任(民法第715条)」です。
- 安全配慮義務違反:労働者の生命や健康を守るために、会社が必要な配慮を怠った状態
- 使用者責任:会社の従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、会社が連帯して損害賠償責任を負うこと
損害賠償と労災保険では、重複する内容の補償を受けることはできません。ただし、損害賠償では、労災保険では補償されない慰謝料などを請求することが可能です。
より手厚い補償を受けるためにも、会社に過失がある労災については、損害賠償請求を検討しましょう。
【関連記事】労災で慰謝料請求はできるか?(不法行為責任に基づく損害賠償請求について)
会社に損害賠償請求を行う方法
労災について、被災労働者が会社に損害賠償請求を行う方法としては、次の3つが考えられます。
【交渉】
会社と直接話し合い、任意に損害賠償を求める方法です。
【労働審判】
労働者と会社間の労働トラブルを解決するため、労働審判委員会が審理・判断を行う手続きです。原則として3回以内の期日で審理を終えるため、早期解決が期待できます。
【裁判】
交渉や労働審判で解決できなかった場合、民事訴訟を提起する方法です。裁判では、口頭弁論や尋問を経て裁判所の判断を仰ぎます。
一定の時間がかかりますが、強制力のある判決を得ることができます。
損害賠償請求にあたっては、いずれの手続きも法的知識や交渉力が求められます。
労働者自身の負担を軽減し、手続きを円滑に進めるためには、弁護士の支援を受けることをおすすめします。
【関連記事】労災で損害賠償請求、請求の方法など
まとめ
労災保険から補償を受けることは、労災によってケガをしたり病気になったりした被災労働者の権利です。労災申請は退職後でも可能であり、必ず手続きを行い、適切な補償を受けるようにしましょう。
また、会社に法的責任が認められる場合には、損害賠償請求を検討することも大切です。この手続きには専門的な知識が必要となるため、労働問題を扱う弁護士に相談すると良いでしょう。
労災無料相談センターでは、労災に関する相談・依頼をお引き受けしています。実績豊富な弁護士が、労災に遭った方に寄り添い、適切な手続きをしっかりサポートします。
もちろん、損害賠償請求にも対応可能です。
労災に関してお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。