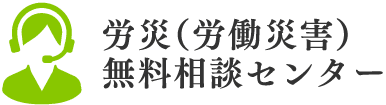製造業は、他の業種と比べて労働災害(労災)の発生件数が多い傾向があります。業務や通勤中には、自分の安全に注意を払うことが重要ですが、それでも事故が完全に防げるわけではありません。
万が一の労災に備えるには、労災の申請手続きや損害賠償の請求方法について事前に把握しておくことが大切です。
そこで今回は、製造業における労災の統計データや実際の事例を紹介しながら、申請手続きの流れや損害賠償請求時の留意点について、わかりやすく解説します。
製造業の労災の発生状況
厚生労働省の「令和5年 労災発生状況」によると、製造業の死亡者数は138人、休業4日以上の死傷者数は27,194人と報告されています。これは業種別で最も多い数値です。
建設業の死亡者数は223人、第三次産業は209人です。
休業4日以上の死傷者数では、製造業が27,194人、第三次産業が21,673人、陸上貨物運送業が16,215人となっています。
製造業では、機械操作や高所作業、危険物の取り扱いなどが多いため、他業種よりも労働災害のリスクが高い傾向にあります。
労災認定される事故の種類
労災と認定される事故には、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
それぞれに法律上の要件が定められており、これを満たした事故については、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づいて補償が受けられます。
業務災害
労働者が業務上の理由でケガや病気になったり、亡くなった場合を「業務災害」といいます。
この場合、以下の2つの要件の両方を満たす必要があります。
- 業務起因性(業務と災害との間に因果関係があること)
- 業務遂行性(労働者が事業主の管理下にある状態であること)
たとえば、勤務中に工場内で機械に挟まれてケガをした場合、両方の要件を満たすため、業務災害に該当します。
一方で、休憩時間中に私用で外出中の事故によるケガは、業務との関係が薄いため業務災害と認められません。
通勤災害
労働者が通勤途中にケガや病気を負ったり、死亡した場合は「通勤災害」に該当します。
労災保険では、「通勤」と認められるのは、自宅と職場を行き来する移動や、職場間の移動など、仕事に関連する決まったルートでの移動です。ただし、出張など仕事そのものの移動は「通勤」には含まれません。
具体的には次のような移動が該当します。
① 自宅と職場の往復
② 一つの職場から別の職場への移動
③ 上記①に先立つ、または後に続く別の自宅への移動
上記のような通勤中でも、大きく道を外れたり、途中で長く立ち寄った場合は、そのあとの移動は「通勤」とは認められません。
ただし、買い物や通院など、日常生活に必要な用事のための寄り道であれば、再び通勤ルートに戻った時点から「通勤」として扱われます。
製造業の労災事例
前述のとおり、製造業は労災リスクの高い業種です。ここでは、厚生労働省が公表している製造業で実際に起こった労災事例を2つご紹介します。
事例1:配管修理による油漏れ火災
ある石油・石炭製品製造業にて、配管の仕切り板を外し修理を行っていたところ、空気圧作動弁が突如動き、大量の油が流出しました。油は、階下で使用していた電気器具や火器に着火し、大規模な火災となりました。
結果として、逃げ遅れた4名が死亡することとなりました。
この労災事故は、空気圧作動弁を施錠するなど、安全対策を怠ったことが原因とみられています。
事例2:かんな盤清掃中の衣服巻き込み事故
ある木工加工所にて、ヘラを使い、かんな盤の下部ローラーに付着した木くずを取り除く作業をしていた従業員が、背面にあったローラーに衣服を巻き込まれケガをしました。従業員は上半身を強く圧迫され負傷し、長期休職を余儀なくされました。
この労災事故は、ローラーを停止させていなかったことや2人以上で作業を行っていなかったことなど、安全管理の不足が原因とみられています。
労災保険の給付の種類
業務中や通勤途中に負ったケガ・病気・死亡について、労働基準監督署により労災と認定された場合、被災労働者またはその遺族は、労災保険から給付を受けることができます。
労災保険とは、労働中や通勤中に発生した災害に対して、労働者に補償を行う国の保険制度です。
事業主は、従業員を1人でも雇用していれば、その労働者全員を労災保険に加入させ、保険料を負担する義務があります。
そのため、原則としてすべての労働者が労災保険に加入しており、労災が発生した際は給付を受けられる仕組みになっています。
労災保険には、傷病の状況に応じて以下の給付があります。
- 療養補償給付:労災による治療や通院に必要な医療サービス・費用を補償する給付
- 休業補償給付:療養のために仕事を休まざるを得ない場合に支払われる給付
- 傷病補償年金:療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても症状が治らず、一定の障害状態にある場合に支給される年金
- 障害補償給付:治療後に後遺障害が残った場合に支給される給付
- 介護補償給付:後遺障害により介護が必要な場合に支給される給付
- 遺族補償給付:労災により労働者が亡くなった際、その遺族に支給される給付
- 葬祭給付(葬祭費):労災によって死亡した労働者の葬儀を行った人に支給される給付
※業務災害では「〇〇補償給付」、通勤災害では「〇〇給付」と表記されます。
これらの給付を受けるには、それぞれ定められた支給要件を満たす必要があります。
また、給付の申請は労働者または遺族が行い、労働基準監督署による労災認定を受けることが必要です。
労災保険の申請手続きの流れ
労災保険の給付を受けるためには、次のような手続きが必要です。
1.医療機関の受診
労災によってケガや病気を負った場合は、まず会社に報告し、その後、医療機関を受診します。
受診時には、「労災による受診」であることを伝え、健康保険証は使用しないよう注意が必要です。
労災指定病院(労災保険指定医療機関)で治療を受けた場合、自己負担は不要です。
一方、指定病院以外で治療を受けた場合は、いったん全額を立て替えた上で請求手続きを行う必要があります。
2.請求書の作成・提出
次に、給付金の請求書を作成します。たとえば、医療費の補償を受ける場合は、「療養補償給付支給請求書」を用意し、必要事項を記入します。
会社に事業主証明欄の記入を依頼する必要があります。
労災指定病院で治療を受けた場合は、そのまま病院窓口へ提出します。
指定病院でない場合は、医療機関に証明欄を記入してもらったうえで、所属事業所を管轄する労働基準監督署へ提出します。
3.労働基準監督署の調査
労働基準監督署は、請求書の内容を確認し、必要に応じて調査を行います。
この際、被災者本人や会社関係者への聞き取りが行われることもあります。
4.労災認定・不認定の決定、通知、振り込み
調査終了後、労働基準監督署長が労災かどうかを判断し、支給または不支給の決定を行います。
結果は被災労働者に通知され、給付が認められた場合は、指定口座に振り込まれます。
なお、会社が申請手続きを代行してくれるケースもありますが、必ずしも対応してくれるとは限りません。
会社が対応しない場合には、被災者本人が手続きを行う必要があるため、流れを理解しておくことが大切です。
【関連記事】労災を申請する流れを徹底解説!病院受診から給付まで
労災保険と損害賠償請求
ここまでご説明したとおり、労災でケガや病気を負ったり死亡したりした場合、労働者やその遺族は労災保険から給付金等の補償を受けることができます。
労災保険の補償は多岐にわたります。しかし、万全ではありません。労災保険では、精神的な苦痛に対する慰謝料は補償されないためです。
そこで検討すべきなのが、損害賠償請求です。労災では、事業主(会社)や第三者に事故発生の法的責任がある場合、損害賠償請求を行うことができます。
損害賠償請求では、慰謝料も請求することが可能です。
事業主に損害賠償請求を行う場合の要件
事業主(会社)に損害賠償請求を行う場合、その代表的な法的根拠としては、以下のようなものが考えられます。
- 安全配慮義務違反:事業主が負うべき職場の安全配慮義務を果たしていないこと
- 使用者責任:従業員が第三者に損害を与えた場合にその雇用主である事業主も賠償責任を負うこと
事業主に上記のような法的責任が認められる場合、被災労働者は事業主に対し損害賠償請求を行うことができます。
上記の中でも多いのは、安全配慮義務違反による賠償請求でしょう。例えば、機械の不具合によるケガや過重労働・パワハラによる精神疾患などは、事業主が安全配慮義務を怠ったことにより発生したと考えられることから、安全配慮義務違反を問うことができる可能性があります。
また、他の従業員が起こした労災事故についても、使用者責任を理由に、会社の責任を問うことは可能です。
第三者に対する損害賠償請求
第三者による過失や故意の行動によって労災が起きた場合には、その第三者に対し損害賠償を請求することも可能です。
例えば、同僚のミスでケガを負った場合にはその同僚に対して、通勤中に自動車と衝突した場合にはその運転手に対して、損害賠償請求を行うことができます。
損害賠償請求の内容
損害賠償請求では、相手方に対し、以下の損害項目を原則として請求できます。
- 治療費・通院費・入院費:医療機関での治療にかかる実費
- 休業損害:傷病により働けなかった期間の減収分
- 逸失利益(いっしつりえき):将来得られるはずだった収入の喪失分
- 介護費用:後遺障害等により日常的な介護が必要となった場合の支出
- 葬儀費用:死亡事故にかかる葬儀関連の費用
- 慰謝料:精神的苦痛に対する金銭的な補償
労災保険でも、療養補償給付(治療費)、休業補償給付(休業補償)、障害補償年金等に基づく補償(逸失利益相当)、介護補償給付(介護費用)、葬祭料(葬儀費用)については補償されます。
ただし、慰謝料については労災保険の給付対象外であり、加害者(例:事業主や第三者)に対して損害賠償請求をすることでのみ補償されます。
精神的損害を補償してもらうには、民事上の損害賠償として請求する必要があります。
損害賠償請求を行う際の注意点
損害賠償請求を行う際には、以下の2点について正確に理解しておくことが大切です。
労災保険と損害賠償では、補償が重複する場合は受け取れない
労災保険と損害賠償の両方から同じ内容の補償を受けることはできません。
この「二重取りの禁止」は、労災保険法第12条の8に基づき、損害賠償請求で得た額がある場合には、労災保険の給付が調整される仕組みとなっています(特別支給金を除く)。
たとえば、労災保険から療養補償給付(治療費)を受けている場合には、損害賠償として同じ治療費を重ねて請求することはできません。
また、休業補償給付(休業中の賃金補償)を受け取っている場合も、損害賠償で同じ期間の休業損害をそのまま重複して請求することは認められません。
ただし、慰謝料(精神的苦痛に対する補償)など、補償の内容が労災保険の給付と重ならない部分については、損害賠償として別途請求することが可能です。
損害賠償では被災労働者の過失が考慮される
労災保険の給付は、被災労働者に過失があっても支給されます。
一方で、損害賠償では、被災労働者に過失があると、その分だけ賠償額が減額される可能性があります。
この考え方は「過失相殺(かしつそうさい)」と呼ばれます。
過失相殺とは、労働者の落ち度の程度に応じて、損害賠償額を減額する仕組みです。
具体的な減額割合は法律で一律に決まっておらず、過去の判例や事情に基づいて、事案ごとに交渉または裁判所の判断で決まるのが実情です。
そのため、損害賠償請求を行う際には、専門的な判断が必要になることから、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
【関連記事】労災の損害賠償請求をわかりやすく解説:計算方法・判例等も紹介
まとめ
労災に備えるためには、労災保険の補償内容や申請手続きだけでなく、損害賠償の可能性についても理解しておくことが重要です。
これにより、万が一労災に遭った場合でも、適切に対応でき、受けられる補償の内容が充実する可能性があります。
ただし、損害賠償請求は、専門的な知識や判断が求められる場面が多くあります。
請求を検討する際は、労働問題に詳しい弁護士に相談し、法的判断や交渉を依頼することが望ましいでしょう。
労災無料相談センターでは、労災に関するご相談を受け付けています。
実績豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に応じて適切なアドバイスを行い、解決に向けた手続きをサポートします。
労災トラブルでお困りの方や、損害賠償請求をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。