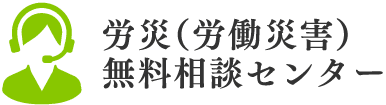事業主に雇用され働く人を、労働者と呼びます。労働者が労災(労働災害)に遭った場合には、労災保険(労働者災害補償保険)から給付が行われることが、労働者災害補償保険法(労災保険法)で定められています。
では、労災保険の対象となる労災には、どのようなケースが該当するのでしょうか。また、労災保険からはどのような給付が行われるのでしょうか。
今回は、労災(労働災害)とは何なのかを、労災保険の給付内容や手続きと併せて、わかりやすく解説します。
労災(労働災害)とは
労災とは、労働災害を略した言葉で、業務に起因して労働者が負った負傷や病気、死亡などのことを指します。例えば、業務中や労災保険法で「通勤災害」として認められる場合の通勤中に起こった以下のようなケースが労災に該当します。
- 業務中に機械に腕を挟まれケガを負った
- 通勤災害に該当する場合、通勤中に事故に遭い骨折した
- 屋外での作業中に熱中症にかかった
- 業務による強い心理的負荷が原因でうつ病を発症した
- 継続的な長時間労働により過労死した など
事故の内容はケースによって異なりますが、そのケガや病気、死亡が業務に起因する場合、それは労災に該当します。
労災によるケガや病気、死亡は、労災保険(労働者災害補償保険)による補償対象となり、被災した労働者や遺族には給付金が支給されます。
労災が発生しやすい業種ランキング
労災の発生しやすさは、業種によって大きく異なります。
ここでは、厚生労働省の情報をもとに、業種ごとの労災発生率を確認していきましょう。
【業種別の労災による死亡者数】
| 業種 | 死亡者数 | 割合 |
| 建設業 | 223人 | 約29.5% |
| 第三次産業(サービス業全般) | 209人 | 約27.6% |
| 製造業 | 138人 | 約18.2% |
| 陸上貨物運送事業 | 110人 | 約14.5% |
| 林業 | 29人 | 約3.8% |
| その他 | 46人 | 約6.0% |
| 合計 | 755人 | – |
【業種別の労災による死傷者数(休業4日以上)】
| 業種 | 死傷者数 | 割合 |
| 製造業 | 27,194人 | 20.0% |
| 小売、社会福祉施設、清掃・と畜、飲食店以外の第三次産業 | 26,819人 | 19.8% |
| 陸上貨物運送事業 | 16,215人 | 11.9% |
| 小売業 | 16,174人 | 11.9% |
| 建設業 | 14,414人 | 10.6% |
| 社会福祉施設 | 14,049人 | 10.3% |
| 清掃・と畜業 | 6,850人 | 5.0% |
| 飲食店 | 5,710人 | 4.2% |
| その他(林業など) | 7,946人 | 5.8% |
| 合計 | 135,371人 | – |
(参照:厚生労働省『令和5年 労働災害発生状況』)
この結果からは、特に建設業や第三次産業(サービス業全般)において、労働者が死亡に至る重大な労災事故が多数発生していることがわかります。
また、死亡者と負傷者を合わせた人数は製造業で特に多いことから、製造業では労災による負傷事故が多く発生していることも読み取れます。
労災の種類
労災の種類は、「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分かれます。この種類によって、労災の認定基準は異なります。
業務災害
業務災害とは、業務上の原因で発生した労働者のケガや病気、死亡のことを指します。業務と事故に因果関係がある場合には、その事故は業務災害として、労災保険の補償対象になります。
業務と事故の因果関係を判断するためには、次の2点が重要視されます。
- 業務遂行性(労働者が業務に従事していたと認められること)の有無
- 業務起因性(業務が原因となって発生した事故や健康障害であること)の有無
これらの両方を満たす事故については、業務災害(労災)が認められます。反対に、どちらか一方でも満たさない場合、その事故は業務災害とは認められません。
通勤災害
通勤災害とは、通勤中の事故による労働者のケガや死亡のことです。
「合理的な経路・手段で行う住居から就業の場所への移動」という通勤の定義を満たす中で起きた事故は、通勤災害として認められます。しかし、認められている通勤経路・手段から外れたり、業務に関係のない目的で長時間寄り道をした場合、その後の移動は通勤とはみなされません。
ただし、日用品の購入や選挙の投票、医療機関の受診など、日常生活に必要な行為を目的とした短時間の寄り道は認められており、その後元の通勤経路に戻れば、引き続き通勤とみなされます。
労災の原因
労災が起こる原因としては、以下のようなものが考えられます。
人的要因(不安全行動)
人的要因(不安全行動)とは、労働者のミスや不注意、規則違反などを指します。
厚生労働省では、上記の原因について、以下のようにより細かな項目を提示しています。具体的には、以下のような行動が該当します。
- 防護・安全装置を無効にする
- 安全措置の不履行
- 不安定な状態の放置
- 危険な状態を作る
- 機械・装置等の指定外の使用
- 運転中の機械・装置等の掃除、注油、修理、点検等
- 保護具、服装の欠陥
- 危険場所への接近
- その他の不安全な行為
- 運転の失敗(乗物)
- 誤った動作
(参照:厚生労働省 『職場のあんぜんサイト 安全衛生キーワード』)
物的要因(不安全状態)
物的要因(不安全状態)とは、機械や設備、作業環境の不備や欠陥を指します。
具体的には、以下のような状態が該当します。
- 物自体の欠陥
- 防護措置・安全装置の欠陥
- 物の置き方、作業場所の欠陥
- 保護具・服装等の欠陥
- 作業環境の欠陥
- 部外的・自然的不安全な状態
- 作業方法の欠陥
(参照:厚生労働省 『職場のあんぜんサイト 安全衛生キーワード』)
労災の原因は、労働者本人や作業環境、組織など、さまざまな要因が結びつくことによって、労災へ繋がります。
労災を防止するためには、上記の原因に対し徹底した対策を取ることが重要です。
労災保険とは
労災保険とは、正式には労働者災害補償保険といい、労災によって被災した労働者や遺族への保険給付を行う公的保険制度です。
労災が発生した場合には、労働者や遺族は労災保険に請求を行うことで、状況に合った種類の給付金を受け取ることができます。
労災保険への加入義務は、事業者にあります。1人でも労働者を雇用している場合、事業者は必ず労災保険に加入しなければなりません。ただし、一部の業種では特別加入制度を利用し、個人事業主やフリーランスも労災保険に加入することが可能です。また保険料は、全額事業者が支払います。
加入は正社員に限らず、契約社員や派遣社員、パート、アルバイト、日雇い労働者など、全ての労働者が対象となります。
労災保険の補償の種類
労災保険から行われる主な補償は、次の7種類です。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 傷病(補償)年金
- 障害(補償)給付
- 介護(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料・葬祭給付
各給付の対象や金額についてご説明します。
療養(補償)給付
療養(補償)給付は、労災によるケガや病気の療養に必要な費用またはサービスを補償する給付金です。業務災害の場合は療養補償給付、通勤災害の場合は療養給付と呼ばれます。
この給付では、ケガや病気の治療や手術、入院、薬などが原則として現物給付の形で支給されます。ただし、緊急時など一定の条件を満たせば、自己負担した医療費が払い戻される(費用償還)場合もあります。また、条件を満たす通院費も支給対象です。
療養(補償)給付は、対象のケガ・病気が治ゆ(症状固定)した時まで支給されます。この場合の治ゆとは、一般的に認められた医療を施してもその効果が期待できなくなった状態を指し、完治を指すものではありません。
休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、労働者が労災によるケガや病気で働けなくなった場合に支給される給付金です。その支給要件は以下の3つです。
- 労災による療養のため
- 労働することができず
- 賃金の全部または一部を受けていないこと
この給付は、休業4日目から支給され、上記の要件を満たす限り継続されます。
休業(補償)給付として支給される金額は、まず「給付基礎日額」を基準に計算されます。給付基礎日額とは、原則として労働者の直前3カ月間の平均賃金をもとに算出される額です。 休業(補償)給付として支給されるのは、給付基礎日額の60%相当額です。
さらに、休業特別支給金(労働者災害補償保険法に基づく特別支給金)として給付基礎日額の20%相当額が支給されるため、合計すると給付基礎日額の80%相当額が支払われることになります。
また、休業3日目までの待機期間については、労災保険ではなく、労働基準法に基づき事業主からの補償(平均賃金の60%以上)が行われます。
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金は、労災によるケガや病気の療養を始めてから1年6カ月経っても症状が治ゆしておらず、その障害の程度が「傷病等級」という基準に該当する場合に支給される給付金です。傷病等級とは、長期療養が必要な重い症状を持つ人に対して定められた3段階の等級制度です。
傷病等級に該当する症状と療養が続く限り支給されます。
ただし、傷病(補償)年金を受け取ることになっても、医療費の補助として支給される「療養(補償)給付」は継続されます。 一方で、「休業(補償)給付」は、同じ負傷や疾病に関しては打ち切りになります。
また、傷病等級には、第1級〜第3級まで3つの等級があり、等級が低いほど支給額は高くなります。
障害(補償)給付
障害(補償)給付は、労災のケガや病気が治ゆ(症状固定)したものの、身体に一定の障害が残り、その状態が規定の「障害等級」に該当する場合に支給される給付金です。
障害等級とは、労災保険において障害の重さを判定する基準で、1級が最も重く、14級が最も軽いとされています。
障害等級は1級〜14級まであり、等級によって給付金の種類は以下のように異なります。
- 1級〜7級:障害(補償)年金・障害特別支給金・障害特別年金
- 8級〜14級:障害(補償)一時金・障害特別支給金・障害特別一時金
また、障害等級が低い(数字が小さい)ほど障害の程度は重く、給付金の金額は高くなります。
介護(補償)給付
介護(補償)給付は、障害(補償)年金を受給している方のうち、障害等級が1級の方、または2級のうち「精神・神経系統」または「胸腹部臓器」に関する障害を持つ方が対象です。現在、家族や介護サービスによる介護を受けている場合に支給される給付金です。
この給付は、以下の要件を満たす場合に適用されます。
- 一定の障害の状態にあること
- 現に介護を受けていること
- 病院や診療所に入院している場合は支給対象外
- 介護老人保健施設や介護医療院などの施設に入所している場合も支給対象外
介護の必要度によって支給額が異なります。 常時介護が必要な場合と、随時介護(部分的な介護)が必要な場合で支給上限額が異なり、常時介護の方が高くなります。
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、労災によって亡くなった労働者の遺族に対して支給される給付金です。
この給付には2種類あります。
- 遺族(補償)年金
- 遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金は、亡くなった労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、生計を維持していた人に支給されます。受給順位が定められており、配偶者と子が最優先となります。
一方、年金を受け取れる遺族がいない場合には、遺族(補償)一時金が支給されます。
また遺族(補償)給付は、遺族特別支給金および遺族特別一時金とともに支給され、その金額は遺族の人数によって変わります。
葬祭料・葬祭給付
葬祭料・葬祭給付は、労災で亡くなった労働者の葬儀費用を補助するために支給される給付金です。業務災害の場合は「葬祭料」、通勤災害の場合は「葬祭給付」と呼ばれます。
原則として、遺族に支給されます。 ただし、遺族がいない場合や会社が葬祭を行った場合は、実際に葬儀を行った者(会社など)に支給されます。
この給付では、「31万5000円+給付基礎日額の30日分」または「給付基礎日額の60日分」のうち、金額の高い方が支給額として採用されます。
以上の労災給付の他にも、労災保険は、会社の健康診断で異常が認められた方に対する二次健康診断等給付なども実施しています。
労災の認定基準
労災の認定基準は、労働者が負った傷病の種類によって異なります。ここからは、労災の認定基準を「業務災害によるケガ・死亡」「腰痛」「精神障害」「脳・心臓疾患」の4つに分けて解説していきます。
業務災害によるケガ・死亡の認定基準
業務災害によるケガや死亡の労災認定基準は、以下のとおりです。
- 業務遂行性が認められること
- 業務起因性が認められること
業務遂行性とは、労働者が事業主の指揮命令のもと業務を行っている最中に発生した事故であることを指します。事業主の管理下にあっても業務と無関係な行動中の事故は、労災とは認められません。
一方の業務起因性とは、業務に関連する作業が原因でケガや死亡が発生したことを指します。私的な行動や業務外の要因による事故は、労災とは認められません。
腰痛の認定基準
腰痛についての労災認定基準は、「災害性の原因によるもの」と「災害性の原因ではないもの」の2種類に分類されています。
【災害性の原因による腰痛の場合】
- 腰の負傷やその原因となった急激な力が、業務中に発生した突発的な出来事によって生じた場合に認められる
- 腰にかかった力が原因となって腰痛を発症した場合や、持病(既往症)が悪化した場合に認められる
【災害性の原因ではない腰痛の場合】
- 突発的な出来事ではなく、慢性的に腰に過度な負担がかかる業務(重いものを取り扱う業務など)に従事する労働者に発症した腰痛であり、作業期間や仕事内容から業務が原因と認められる場合に認められる
それぞれの要件を満たす腰痛については、労災と認定されます。
ただし、突発的に腰痛が起こる「ぎっくり腰(急性腰痛症)」については、労災は認められません。ぎっくり腰は、日常的な動作の中で起こるものであり、業務との直接的な因果関係を証明することが難しいためです。
精神障害の認定基準
精神障害の労災認定基準は、以下の3要件に分類されます。
- 厚生労働省の認定基準に該当する精神障害を発症していること
- 発症前のおおむね6カ月間に、業務による強い心理的負荷があったと認められること
- 業務以外の心理的負荷や「個体側要因」(性格や既往歴など)が主な原因ではないこと
これらの要件をすべて満たす場合、発症した精神障害は労災と認められます。
上記の心理的負荷の評価には、厚生労働省が定める「心理的負荷評価表」が用いられます。この評価表には、具体的な出来事の事例とその影響度が記載されており、該当する項目を選択することで、要件に適合するかどうかを判断できます。
脳・心臓疾患の認定基準
脳・心臓疾患が労災と認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 発症前に、おおむね6カ月以上の過重業務があったこと
- 発症直前の1週間程度の時期に、特に過重な業務があったこと
- 発症直前から前日までの間に、強い精神的または身体的負荷がかかる出来事や、急激な作業環境の変化などの異常な状況があったこと
労災と認められる可能性のある脳・心臓疾患の種類は以下のとおりです。
- 脳出血(脳内出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止(心臓性突然死を含む)
- 重篤な心不全
- 大動脈解離
労災が認められないケース
次のようなケースでは、労災は認められません。
- 労働者の私的な行動や、業務を逸脱した意図的な行為による事故
- 故意または重大な過失が原因の事故
- 個人的な恨みや業務と関係のないトラブルによる第三者からの暴行
- 業務に関連しない地震や台風などの自然災害による事故
- 休憩時間中や退社後に業務と無関係な目的で寄り道をした際の事故
- 通勤経路を大きく逸脱したり、不適切な手段で通勤したりした場合の事故
これらの事故は、業務との関連性が認められません。したがって、労働者がケガや病気、死亡を負っても、労災保険の補償対象にはなりません。
労災の申請手続きの流れ
労災申請および労災給付の請求は、以下の流れで進めます。
- 医療機関で治療を受ける
- 必要書類を準備する
- 書類を労働基準監督署・労災指定病院へ提出する
- 労働基準監督署による調査が行われる
- 労災認定・不認定の決定と通知が行われる
手順ごとに内容を詳しくご説明します。
1.医療機関で治療を受ける
労災でケガを負ったり病気の症状が出たりしたら、まずは医療機関で治療を受けます。この時、窓口で労災であることを伝えれば、医療機関側は労災として手続きを進めてくれます。
労災による傷病の治療では、労災保険の指定病院を利用するのが一般的です。指定病院なら、労働者は治療費を支払うことなく、現物支給という形で治療を受けることができます(治療費は労災保険から病院へ直接支払われます)。
労災保険の指定外の病院を利用した場合、労働者は一旦治療費や薬代を自分で立て替えなければなりません。その後、療養補償給付(労災保険に基づき、労働者が自己負担なしで治療を受けられる制度)の請求手続きを行うことで、労災保険から労働者の指定口座へ振り込まれます。
2.必要書類を準備する
労災申請の手続きは、多くの場合、所属する会社が代理で行います。しかし、会社が手続きを進めてくれない場合には、労働者自身が手続きを行わなければなりません。
手続きにあたっては、まず労災の申請に必要な書類を準備・作成しましょう。
請求する給付金や状況によって必要な請求書やその他の資料は異なります。書類に不備があると、労災認定までにかかる期間が長引くため、早く給付を受けるには不備がないよう注意が必要です。
また、請求書の作成にあたっては、会社や病院(労災指定病院以外の場合)に証明欄を記入してもらう必要があります。
会社に協力してもらえない場合には、会社証明欄は空白でも構いません。その場合、労働基準監督署が事実確認のため会社や労働者へヒアリングを行います。
3.書類を労働基準監督署・労災指定病院へ提出する
必要書類が揃ったら、職場を管轄する労働基準監督署の窓口へ提出します。会社証明欄が空白の時には、会社の協力を得られなかった旨を担当者に伝えましょう。
また、労災によるケガや病気で治療を受けた場合、療養補償給付の請求書は、原則として労働基準監督署へ提出します。ただし、労災指定病院で治療を受けた場合は、その病院を通じて提出することも可能です。
4.労働基準監督署による調査が行われる
書類の提出が完了したら、労働基準監督署による調査が始まります。この調査では、労働者や会社への事情聴取に加え、労災保険給付の適用要件を満たしているかを確認するための書類審査が行われます。必要に応じて、労災の発生状況を確認するための現場調査が実施されることもあります。
5.労災認定・不認定の決定と通知が行われる
調査が完了したら、労働基準監督署長による労災認定・不認定の判断が行われます。
この結果は労働者に、「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」という形で通知され、認定された場合は後日給付金が振り込まれます。
労災認定の結果が出るまでの期間は、療養補償給付の場合で概ね1か月程度ですが、審査の内容や必要な追加調査によってはさらに時間がかかることもあります。
まとめ
労災保険は、労働者が万が一の事故に遭った場合に、その療養や生活をサポートするための保険です。会社に雇用されている場合、事業主は原則として労災保険に加入しなければなりません(加入義務は会社側にあります)。また、業務に関連してケガなどを負ったときには、健康保険ではなく労災保険が適用されます。
さらに、労災については、会社との間にトラブルが起きたり、損害賠償請求を検討したりするケースもあります。
そのような場合には、労災無料相談センターへご相談ください。弁護士が請求手続きをサポートし、トラブルを解決へと導きます。
労災関連の悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。