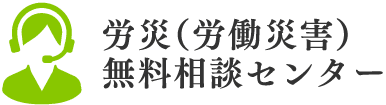会社に雇用されて働く労働者が業務に起因する事故などに遭った場合には、労災保険(労働者災害補償保険)からの補償を受けることができます。
ただし、補償を受けるためには申請手続きを行い、労働基準監督署の審査を経て労災と認定されなければなりません。この労災認定の審査にどれくらいの期間がかかるのか、気になる方は多いでしょう。
そこで今回は、労災申請にあたって労基署に労災認定されるまでの期間はどれくらいなのか、また労災認定までの対応について解説します。
労災認定されるまでの期間
労災に遭った時には、労基署に給付金の請求書を提出し、申請手続きを行います。この申請手続きが完了してから労災認定までにかかる期間は、請求する給付金の種類によって異なります。厚生労働省が示している、主要な給付金ごとの認定までの審査にかかる期間は以下のとおりです。
- 療養補償給付・療養給付:おおむね1カ月(1カ月以上の場合も有り)
- 休業補償給付・休業給付:おおむね1カ月(1カ月以上の場合も有り)
- 障害補償給付・障害給付:おおむね3カ月(3カ月以上の場合も有り)
- 遺族補償給付・遺族給付:おおむね4カ月(4カ月以上の場合も有り)
(参考:厚生労働省『労災保険 申請(請求)のできる保険給付等』)
業務に関連したケガや病気の治療費等を補償する「療養(補償)給付」やケガ・病気で働けなくなった場合に給付される「休業(補償)給付」は、申請からおおよそ1カ月で支給の可否が判断されます。
また、後遺障害が残った場合に給付される「障害(補償)給付」は3カ月程度、労働者が死亡した場合に給付される「遺族(補償)給付」は4カ月程度が、支給決定までの目安として示されています。
ただし、上記の期間はあくまで目安です。他の給付も含め、労災認定までにかかる期間はケースバイケースだと考えてください。
【関連記事】労災認定の審査期間にかかる時間はどれくらい?
場合によって期間は前後する
前章でご紹介したとおり、申請手続きを終えてから労災認定までにかかる期間はケースバイケースです。例えば、療養(補償)給付を受け取る場合の認定までの期間の目安はおおむね1カ月ですが、場合によってはそれ以上の時間がかかることもあります。
労災認定までの期間がケースバイケースであるのは、労基署の調査や手続きの進み具合によるためです。 調査の進行は、各事故が業務災害として認定されやすいかどうかや、労基署の業務量によって異なります。
業務災害であることが明確なケースでは、労災認定までの期間が短くなります。 一方、業務との因果関係の判断が難しいケースでは、期間が長くなる傾向があります。
労災認定の判断が長引くケース
労基署による労災かどうかの判断が長引き、労災認定が遅くなるケースとしては、次のようなケースが考えられます。
精神障害を労災申請するケース
うつ病などの精神障害も、労災と認められることがあります。
しかし精神障害の場合、ケガなどと比べ、業務との因果関係を立証することは難しいです。業務によって発症した精神障害かどうかを判断するには、個々の申請について、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷、労働者の個人的要因(既往歴など)を総合的に検討する必要があります。そのため、審査には数カ月以上を要する場合もあります。
精神障害の労災認定基準は2009年に策定され、2011年に改正されました。 これにより、それまでと比べてより明確で迅速な判断が可能になりました。
しかし、それでもなお、外傷などの身体的な負傷に比べて精神障害の労災認定には時間がかかるのが現状です。 また、精神障害については、申請件数に対する認定件数の割合も例年20〜30%程度と低水準が続いています。
【関連記事】精神障害の労災認定
障害(補償)給付を請求するケース
労災事故でケガを負い、療養を行った後に症状が固定し(症状固定)、一定の後遺障害が体に残った場合、労働者は労災保険の障害(補償)給付を請求できます。
この給付を受けるには、体に残った症状が1級〜14級の障害等級表に該当する必要があり、等級によって給付金の額は変わります。
障害(補償)給付の申請は、症状固定後にしか行えません。そのため、労災事故直後に受け取ることはできません。
また、障害(補償)給付および等級の認定には、労働者との面談や医師への聞き取り、医療記録の確認など多くの調査が必要です。そのため、判断には数カ月以上かかる場合もあります。
労災認定が遅い場合は労働基準監督署に問い合わせるのが望ましい
申請後、長期間経っても労災認定・不認定の判断が行われない場合は、手続きを行った労働基準監督署に問い合わせ、状況を確認しましょう。審査の進捗を把握することで、「自分の労災について審査は進んでいるのだろうか」という不安は軽減されます。場合によっては、認定までのおおよその期間を教えてもらえるかもしれません。
労災認定が遅れ、給付を受けられない期間が長くなると、労働者の生活に影響を及ぼします。そのため、早めに労基署に問い合わせることが重要です。
【関連記事】労災の申請を労働基準監督署にする方法|申請できる怪我や病気、受け取れる給付も解説
労災認定されるまでに損害賠償の請求も可能
会社が安全配慮義務を怠るなどして労災発生の責任を負う場合、労働者は労災保険の給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できます。
なるべく早く補償を受けるためには、労災認定を待たずに損害賠償請求の手続きを進めるのも有効です。
ただし、労災保険と損害賠償の両方から重複する内容の補償を受けること(補償の二重取り)はできません。先に損害賠償による補償を受け取った場合、その分の補償は労災保険の給付金から差し引かれます。
また、損害賠償では相手側に慰謝料を請求することができます。労災保険には慰謝料の補償がないため、二重取りにはなりません。
【関連記事】労災で慰謝料請求はできるか?(不法行為責任に基づく損害賠償請求について)
まとめ
申請手続きから労災認定・不認定の判断が行われるまでには、一定の時間がかかります。給付の種類によりますが、認定までの期間はおおむね1カ月〜4カ月が目安です。ただし、ケースによってさらに時間を要することもあります。 特に精神障害や後遺障害の労災申請は、審査が複雑なため、認定までに長期間かかることがあります。
また、労災事故では労災保険の給付に加え、会社に適切な安全対策を怠った責任がある場合、損害賠償を請求できることがあります。例えば、十分な安全設備を整えていなかったり、長時間労働を強いていたりした場合が該当します。損害賠償の手続きには法律の専門知識が求められるため、弁護士に依頼すると良いでしょう。
労災に関するトラブルにお悩みの方、損害賠償請求を検討している方は、労災無料相談センターへご依頼ください。弁護士が必要な手続きをサポートし、最良の方法で問題を解決へと導きます。
どなた様も、まずはお気軽にご相談ください。