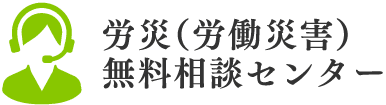労働者が労災で亡くなった場合、その労働者の遺族は、労災保険に対し「遺族(補償)年金(いわゆる労災遺族年金)」または「遺族(補償)一時金等の給付」を請求することができます。
ただし、遺族(補償)年金・一時金にはいくつかの条件が定められており、条件を満たす場合にしか給付金は支給されません。では、その条件とはどのようなものなのでしょうか。
今回は、遺族(補償)給付の中でも年金型に着目し、その受給条件や支給額、いつまでもらえるのかなどをわかりやすく解説していきます。
労災遺族年金の受給条件
労災の遺族年金とは、労災保険から支給される遺族補償年金(業務災害)または遺族年金(通勤災害)のことです。労働者の遺族が遺族年金を受け取るためには、次の受給条件を満たす必要があります。
【遺族(補償)年金の受給条件】
- 被災した労働者が亡くなったとき、その収入によって生計(一部でも可)を維持していたこと
- 次に挙げる遺族のうち、順位が最も高い人(最先順位者)に該当していること ※以下の一覧は、受給できる優先順位の順に記載されています。
- 妻または60歳以上もしくは一定障害(障害等級5級以上)のある夫
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
- 60歳以上か一定障害の父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
- 60歳以上か一定障害の祖父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
(出典:厚生労働省パンフレット『遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続』)
遺族(補償)年金は、上記2つの条件に該当する最先順位者に支給されます。もし最先順位者が死亡したり再婚したりしたことで受給権を失った場合には、次の順位の遺族が受給権を引き継ぐことができます。
ちなみに、上記の「妻」または「夫」などの配偶者には、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係にあったと認められる者(いわゆる事実婚の配偶者)も含まれます。
55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹については、「若年停止」という制度により、60歳になるまで給付金の支給は行われません。
【関連記事】内縁の妻は遺族補償年金を受給できるか?
労災遺族年金はいつまでもらえる?
次に、一度受給が始まった年金がいつまで続くのかについて解説します。
遺族(補償)年金は、受給者が以下のいずれかの条件に該当した場合に支給が終了します。
つまり、それまでは基本的に支給が続きます。
【受給が終了する条件(受給権の消滅事由)】
- 受給者が死亡したとき
- 婚姻(再婚)したとき
- 親や祖父母などの直系血族、または配偶者の親といった直系姻族以外の人の養子となったとき
- 養子縁組を解消する「離縁」により、亡くなった労働者との親族関係が終了したとき
- 子・孫・兄弟姉妹が、18歳に達した日以後の最初の3月31日を過ぎたとき(障害状態にある場合を除く)
- 障害の状態にある受給者(夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が、その障害状態でなくなったとき
(参考:e-Gov法令検索『労災保険法 第16条の4』)
これらに該当した場合、遺族年金の受給は終了します。
逆に言えば、これらに該当しない限りは、年金を継続して受け取ることが可能です。
また、受給者がこれらの理由で受給資格を失った場合でも、前述の「受給条件」に記載された遺族の優先順位において、次の順位にあたる遺族が要件を満たしていれば、その人が新たに年金を受け取ることができます。
労災遺族年金の支給額
労災保険の遺族(補償)給付では、遺族(補償)年金、遺族特別支給金(遺族特別一時金)、遺族特別年金(遺族特別支給金(年金))の3種類の給付金が支給されます。その具体的な支給額は遺族の人数によって、以下のように異なります。
| 遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金(遺族特別一時金) | 遺族特別支給金(年金) |
| 1人 | 給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻、一定障害のある妻については175日分) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(55歳以上の妻、一定障害のある妻については175日分) |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |
| 4人 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
(参考:厚生労働省パンフレット『遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続』)
給付基礎日額とは、労働基準法に基づいて、平均賃金を日額に換算した金額のことを指します。算定基礎日額とは、労災発生前の直近1年間に労働者が受け取った賃金総額を365で割った金額を指します。
ただし、上記の表に記載された金額は、受給権者一人ひとりが受け取れる金額を示すものではありません。受給権者が複数人いる場合、表の金額を人数で等分した金額が、個々が受け取れる給付金の金額となります。
例えば、遺族数が3人で、給付基礎日額が10,000円の場合、遺族(補償)年金の総額は223日分で223万円となります。
この金額は遺族全体に支給されるため、1人あたり約74万円(223万円÷3人)が支給されることになります。
労災遺族年金の請求時効
労災保険の給付金請求には、時効が設定されています。遺族(補償)年金の場合の時効は、以下のとおりです。
【遺族(補償)年金の請求時効】
- 被災労働者が亡くなった翌日から5年
時効を過ぎると、遺族が持つ給付金の受給権は消滅してしまいます。
ちなみに、他の給付金にも時効は設定されており、療養(補償)給付・休業(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)・介護(補償)給付は2年、障害(補償)給付は5年、傷病(補償)年金は2年となっています。ただし、給付金の種類によって、いつから時効の期間を数え始めるかは異なるので注意が必要です。
労災保険の補償を確実に受け取るには、時効に注意して早めに手続きを進めましょう。
労災遺族年金の前払い
労災保険の遺族(補償)年金には、前払いの制度が用意されています。給付金の受給権を持つ遺族は、一度のみ、年金の前払いを受けることが可能です。
既にご紹介したとおり、遺族(補償)年金では、若年停止という制度により、60歳からしか支給を受けられない場合があります。しかし、若年停止の場合でも、前払いを利用することはできます。
遺族(補償)年金の前払いでは、200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分の5つから、受給権者が前払いを希望する金額を選ぶことができます。
前払いを受けた分は、将来受け取るはずだった年金から差し引かれるため、その分の支給が一時的に止まります。
たとえば600日分を前払いで受け取った場合は、以後の支給が600日間停止され、600日分を使い切った後に再び年金の支給が再開されます。
年金の前払い制度には、「被災労働者が亡くなった日の翌日から2年」という時効が設定されています。時効を過ぎた後には、この制度を利用することはできません。
また、遺族(補償)年金の前払い制度は、すでに年金の受給を始めている場合でも、次の2つの条件をどちらも満たしていれば利用できます。
① 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年以内であること
② 給付金の支給決定通知を受け取った日の翌日から1年以内であること
遺族年金を受け取れない場合の「一時金制度」
労災保険の遺族(補償)年金は、一定の条件を満たさない場合、受け取ることができません。
とはいえ、遺族(補償)年金を受け取れないからといって、労災保険からの補償をまったく受けられないわけではありません。
このようなケースのために、「遺族(補償)一時金」という制度が用意されています。
遺族(補償)一時金とは、以下のケースで支給される一時金型の給付金のことです。
- 被災労働者死亡時に、遺族(補償)年金を受け取ることができる遺族がいない場合
- 遺族(補償)年金の受給権者が全て失権し、その時点で支払われた年金や前払い一時金の額が給付基礎日額の1,000日分以下である場合
ただし、遺族(補償)一時金にも以下のような受給順位が定められています。この場合も、最先順位者が給付金を受けることになります。
- 配偶者
- 被災労働者の死亡時にその収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
- その他の子・父母・孫・祖父母
- 兄弟姉妹
給付金の額(ケース別)
【被災労働者死亡時に、遺族(補償)年金を受け取ることができる遺族がいない場合】
- 遺族(補償)一時金:給付基礎日額の1,000日分
- 遺族特別支給金:300万円
- 遺族特別一時金:算定基礎日額の1,000日分
【遺族(補償)年金の受給権者が全て失権し、その時点で支払われた年金や前払い一時金の額が給付基礎日額の1,000日分以下である場合】
- 遺族(補償)一時金:給付基礎日額の1,000日分から既に支給された金額を差し引いた額
- 遺族特別支給金:支給されない
- 遺族特別一時金:算定基礎日額の1,000日分から既に支給された金額を差し引いた額
遺族(補償)一時金の請求時効も、遺族(補償)年金と同じく、被災労働者が死亡した翌日から5年に設定されています。
まとめ
労災の遺族年金(正式には「遺族(補償)年金」)は、残された遺族の生活を守るための重要な補償です。受給条件はやや複雑ですが、条件を満たす場合には、必ず時効内(被災労働者が亡くなった翌日から5年以内)に手続きを行うようにしましょう。
また、「遺族(補償)年金」の受給条件を満たさない場合でも、「遺族(補償)一時金」の受給権が発生する可能性があります。制度の内容がわかりにくかったり条件への該当の可否を判断できなかったりする場合には、労働問題を扱う弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けると良いでしょう。
労災無料相談センターでは、労災に関するお悩みの相談を受け付けています。
法律相談と聞くと、その固いイメージから「こんなことを相談していいのかな?」と考える方もいるかもしれませんが、躊躇する必要はありません。弊所では、実績豊富な弁護士が明るく・わかりやすくアドバイスを行います。もちろん必要な場合には、労災保険の申請手続きから会社への損害賠償請求まで手厚くサポートします。
どなた様も、まずはお気軽にお問い合わせください。