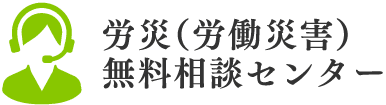会社に雇用されて働く人が労災に遭ったときには、労働災害に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
なぜなら、労災申請には一定の書類や証明資料の提出など、煩雑な手続きが必要とされるためです。また、発生した労災について会社や第三者との間で紛争に発展する可能性も決して低くはありません。
弁護士の手を借りれば、これらの問題を解消するとともに、被災労働者は多くのメリットを得ることができます。
そこで今回は、労災事故について弁護士に相談・依頼することのメリットや弁護士の選び方について、わかりやすく解説します。
労働災害とは
事業主に雇用されて働く労働者が、業務に起因して負ったケガや病気、死亡などは、労働災害(労災)と呼ばれます。通勤途中の災害も、通勤災害として労災に含まれます。
例えば、製品の製造中に機械の操作を誤って腕をケガした場合や、通勤中に車に轢かれて骨折した場合などが労災に該当します。
労災による傷病や死亡は、公的保険である労災保険の補償対象です。労災保険には、療養(補償)給付や休業(補償)給付など多様な給付金が用意されており、労災に遭った労働者はその状況に応じた給付を受けることができます。
また、労災保険への加入は、1人以上の労働者を雇用している事業主に義務付けられており、その保険料は事業主が全額負担します。
【関連記事】労災(労働災害)とは?種類や申請手続き等をわかりやすく解説
労働災害の種類
労災は、その状況によって「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。それぞれの定義と要件を確認していきましょう。
業務災害
業務災害とは、労災の中でも、労働者が業務に起因して負ったケガや病気、死亡などを指すものです。
業務災害が認定されるためには、事故発生時の状況が以下の要件を満たしていなければなりません。
【業務災害の認定要件】
- 業務遂行性がある
- 業務起因性がある
業務遂行性とは、「労働契約にもとづき、労働者が事業主の支配管理下にある状態」を指します。
これに対して業務起因性とは、「事故と業務に一定の因果関係があること」を指します。
これら両方の要件を満たす場合、対象の事故や傷病は業務災害として認められます。
しかし、どちらか一方でも条件を欠く場合には、業務災害として認められず、労災保険の補償も受けることができません。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤により負ったケガや病気、死亡などを指すものです。
通勤災害が認定されるためには、事故発生時の状況が以下の「通勤」の定義を満たしていなければなりません。
【通勤の法的定義】
就業に際し、労働者が次に掲げる移動を、合理的な経路および方法により行うこと。ただし、業務の性質を有するものを除く。
- 住居と就業場所との間の往復
- 就業場所から他の就業場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
(参考:e-Gov法令検索「労災保険法第7条2」)
つまり、通勤と認められるのは、自宅から職場まで、無駄な寄り道をせず、通常使われる道や手段で移動した場合のみです。
もしその途中で寄り道をしたり、大きく道を外れたりした場合、その後の移動は「通勤」とは認められなくなります。
ただし、日常の買い物や通院など、厚生労働省が認める生活に必要な用事のために途中で寄った場合には、再び元のルートに戻れば、その後の移動も通勤と認められます。
過労死・過労自殺も労働災害として認められている
労災と認められるのは、突発的な事故によるケガや過酷な環境での作業による病気(じん肺症、肺がんなど)だけではありません。
過労死や過労による自殺も、要件を満たせば、労災として認められる可能性があります。
【過労死(脳・心臓疾患)の労災認定要件】
- 長期間の過重業務
- 短期間の過重業務
- 特に負荷がかかった異常な出来事
(参考:厚生労働省『脳・心臓疾患の労災認定』)
過労死の場合、上記の要件のいずれかを満たすことで、労災が認定される可能性があります。
【過労自殺の労災認定要件】
- 労災の対象となる精神障害を発病している
- 業務による強い心理的負荷が認められる
- 業務以外の心理的負荷が主な原因ではない
(参考:厚生労働省『精神障害の労災認定』)
過労自殺の場合、上記の要件を総合的に勘案して、労災認定・不認定の判断が行われます。
【関連記事】過労死ラインとは?何時間なのか、どのくらい違法なのか
会社が労災保険の給付に協力しない場合がある
労災が発生した場合、多くの会社は労働者に代わって労災申請手続きを進めます。労働者自身が手続きを行う場合でも、速やかに事業主の記入欄を記入してくれるでしょう。
しかし、中には労働者が労災保険の給付を受けることを嫌がり、これらの手続きに協力しない会社があるようです。
会社が労働者の労災給付を嫌がる背景には、「労災が発生すると、会社の負担する保険料が増えることがある」「保険の未加入や保険料の滞納を知られたくない」などの理由があると考えられます。しかし、労災給付を受けるのは労働者の当然の権利です。会社がその手続きを妨害したり協力を拒否したりすることは、法律で義務付けられた協力義務に違反するため、認められるものではありません。
労災申請の手続きは会社の協力なしでも進められますが、会社とトラブルになった場合には、弁護士へその旨を相談するようにしましょう。
労災事故で弁護士に相談するメリット
労災事故に遭ったときには、労災問題を扱う弁護士への相談を検討しましょう。弁護士のサポートを受けることで、被災労働者は以下のようなメリットを得ることができます。
労災保険についての助言をもらえる
労災申請を行なって労災保険からの補償を受けるためには、請求書の作成や添付書類の準備が必要です。請求書については、複数の種類の中から自分の労災状況に合った給付金のものを使う必要があり、添付すべき書類も状況によって異なります。
自分がどの給付金を請求できるか、必要な書類や書き方などを正しく判断し手続きを進めるためには、労災に関する一定の知識が必要です。しかし、一般的な労働者で労災について詳しいという方は少ないでしょう。
弁護士に依頼すれば、用意すべき書類や手続きについて手厚いサポートを受けることができます。労災問題の知見を持つ弁護士のサポートにより手続きはスムーズに進み、労働者の負担も軽減されるでしょう。
適正な後遺障害等級認定を得られる
労災による傷病が治ゆしたときに、その状態が「後遺障害等級」という基準に該当する場合には、被災労働者は労災保険から障害(補償)給付を受けることができます。
後遺障害等級とは、けがや病気が治ったあとも身体に残る障害の程度を示す基準です。
1級から14級までに分類されており、等級が低いほど障害の程度は重くなります。
つまり、労災の後遺障害で適切な補償を受けるためには、正確な等級で認定されることが非常に重要なのです。実際よりも障害の程度が軽いと判断されて、本来よりも等級が高く(=軽い障害と)認定されてしまうと、受け取れる給付金が少なくなるおそれがあります。
等級の判定は、主治医が作成する意見書などをもとに行われます。
労災問題に詳しい弁護士は、その意見書で重視されるポイントをよく理解しています。
そのため、主治医にどのように意見書を依頼すればよいか、どのように受診すれば適切な内容が反映されるかなど、被災労働者に対して的確なアドバイスをすることができます。
また、実際の障害の程度より軽いと判断され、本来よりも高い等級で認定されてしまうことがあります。
そのような場合でも、弁護士が審査請求や訴訟を行うことで、適正な等級に見直される可能性があります。
後遺障害等級ごとの給付金額の違いについては、厚生労働省『労災保険 障害(補償)等給付の請求手続』をご確認ください。
会社への損害賠償請求で交渉力を発揮する
労災事故の発生にあたっては、会社側に損害賠償請求を行えるケースがあります。損害賠償が可能なのは、会社に労災事故発生の法的責任(安全配慮義務違反や不法行為責任など)がある場合です。
労災保険では慰謝料が支払われませんが、損害賠償では対象となるため、十分な補償を受けるには請求を検討すべきでしょう。
損害賠償請求にあたって、弁護士は、法的知識や経験を活かし、会社に対して強い交渉力を発揮することができます。弁護士が入ることで、会社側の態度が変わる場合もあるでしょう。
より有利かつスムーズに損害賠償請求を行うためにも、弁護士の手を借りることは効果的です。
労働者の権利を守ってくれる
労災保険の利用は労働者の当然の権利です。しかし会社によっては、労災保険を利用した労働者に対し、退職勧奨を行ったり嫌がらせをしたりと、不当な扱いをするケースがあるようです。
このような不当な扱いを受けた場合でも、弁護士に依頼すれば、法律を盾に会社と戦うことができます。立場が弱くなりやすい労働者ですが、弁護士を味方につければ、会社の不適切な対応から自身の権利を守ることが可能です。
【関連記事】労災事故で弁護士に相談・依頼するメリット:会社への損害賠償請求等についても解説
労災事故で弁護士に相談するデメリット
前述のとおり、労災事故について弁護士に相談することには多くのメリットがあります。
ただし、一方でデメリットがある点にも注意しなければなりません。それは、「費用がかかること」です。
弁護士に相談したり依頼したりすると、相談料や着手金、成功報酬などの費用が発生します。かかる費用の目安は、以下のとおりです。
【労災問題の相談・依頼にかかる弁護士費用の相場】
- 相談料:30分5,000円〜
- 着手金:10〜30万円
- 成功報酬:獲得金額の10〜20%
- 日当:1〜3万円
- その他実費:交通費、郵便代など
上記はあくまで目安であり、弁護士事務所によって料金形態や価格は異なります。また、近年では初回相談料を無料とする事務所や、着手金を設定せず成功報酬のみで対応する事務所も増えています。どの場合でもある程度の費用は必要になるので、相談前にはその点を理解しておきましょう。
労災事故に強い弁護士の選び方
労災事故についての相談・依頼にあたっては、より手厚い補償を受けるため、またよりスムーズに手続きを進めるためにも、労災問題を得意とする弁護士を選ぶ必要があります。
相談・依頼する弁護士を選ぶ際には、必ず以下のポイントを重視するようにしましょう。
労働者側としての労災対応実績があるか
弁護士選びでは、労働者側として労災問題を扱った実績の有無が大きなポイントになります。優れた実績が多いほど、その弁護士は労災問題に精通しているといえます。
後遺障害等級認定の知識があるか
後遺障害等級認定は給付金額を左右する重要な手続きです。そのため、制度に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。
誠意ある対応が期待できるか
相性の悪い弁護士に依頼すると、ストレスを感じてしまう可能性があります。無料相談などを活用し、弁護士の対応や相性を確認しておきましょう。
【関連記事】労災に強い弁護士の選び方を徹底解説!
まとめ
労災でケガや病気を負ったとき、また家族を亡くしたとき、手間のかかる労災申請や損害賠償請求の手続きを冷静に進められる方は少ないでしょう。負担を軽くしながら然るべき手続きを進めるためにも、弁護士への相談・依頼は有効です。労災問題を得意とする弁護士のサポートを受け、スムーズかつ有利に手続きを進めましょう。
労災事故に遭った方、労災トラブルに巻き込まれた方は、労災無料相談センターへご相談ください。実績豊富な弁護士が、最適な解決策を目指し、誠意を持って対応します。
まずは無料相談をお気軽にご利用ください。