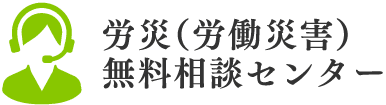仕事中や通勤中に起こる予期しない事故やケガは、労働者にとって大きな負担です。
労災保険制度(労働者災害補償保険制度)は、仕事が原因で負傷や病気、障害、死亡などの被害を受けた場合に補償を受けられる仕組みです。
ただし、手続きが複雑だったり会社が非協力的だったり、後遺障害(事故後に残る障害)認定の難しさなど、多くの課題があります。
このページでは、労働災害(仕事が原因で起こるケガや病気)とは何かを説明し、会社が協力しない場合の対処法や弁護士に相談するメリットを解説します。
さらに、損害賠償請求を進める際のポイント、弁護士費用、労働基準監督署との違いなども紹介します。
適正な補償を受けて権利を守るために、ぜひ最後までお読みください。
労働災害とは
労働災害とは、業務上の理由や通勤によって労働者がケガや病気、障害を負うこと、または死亡することを指します。
例えば、業務で使う機械によるケガ、夏場の作業中の熱中症、長時間労働や職場の嫌がらせ(パワーハラスメント)による精神的な病気などが代表例です。
業務災害と通勤災害
労働災害は「業務災害」と「通勤災害」に分かれ、それぞれの条件を満たす必要があります。
これらの条件をクリアすることが、労災保険への申請や給付を受ける前提です。
業務災害
「業務災害」とは、仕事をしている最中に起こる災害を指します。
次の2つの条件をどちらも満たす必要があります。
- 業務遂行性:労働者が使用者の指揮命令下にある状態であること
- 業務起因性:仕事と災害の間に合理的な因果関係があること
通勤災害
「通勤災害」とは、合理的な経路や方法で通勤中に発生した事故を指します。
具体的には以下のような移動が対象です。
- 住居と職場の間の往復
- 職場から別の職場への移動
- 単身赴任先の住居と帰省先住居の間の移動
会社が労災保険の給付に協力的でないケースがある
労災事故が起きた際は、何よりも迅速に労災保険の給付を確保することが重要です。
しかし、会社が手続きに協力しないケースもあります。
具体的には、労災保険申請に必要な書類への署名や記入を会社が拒む事例が問題です。
会社が協力を渋る背景には、労働基準監督署(労働者の労働条件を監督する行政機関)への報告によって保険料が増えることや、保険料未納による滞納処分のリスクを避けたい事情があります。
このような場合は、まず会社の拒否理由を正確に把握し、誠実に説明して協力を得るよう努めることが必要です。
基本的には話し合いによる解決を目指しますが、当事者間だけでは感情的な対立で解決が難しくなることもあります。
そのため、無理に自力で対応し続けるのではなく、できるだけ早い段階で労災問題に詳しい弁護士などに相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
労災事故で弁護士に相談するメリット
労災事故に関して弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
専門的なサポートを受けられる
まず、以下のような専門的なサポートを受けられます。
労災保険給付を受けるための専門的支援
弁護士は、労災認定や損害賠償請求に詳しく、適正な補償を確保する支援を行います。
特に労災保険は、負傷の状況に応じて複数の給付を組み合わせて請求する必要があります。
以下は主な給付の種類です。
- 療養給付(診察や治療費の補償)
- 休業給付(仕事を休んだ期間の収入補償)
- 障害補償(後遺障害等級1級〜14級に応じた補償)
- 傷病年金(治療が1年6か月を超え、重度障害の場合の年金)
- 介護補償(重度障害による介護費用の給付)
- 遺族補償(労災死亡時の一時金や年金)
- 葬祭料(葬儀費用の補償)
- 二次健康診断等給付(一次健康診断で異常が認められた場合の再検査費用)
弁護士は、事故状況からどの給付を受けられるかを迅速に判断し、必要書類の作成や提出を正確にサポートしてくれるため、ミスやトラブルを防げるでしょう。
適正な後遺障害等級認定を受けるための支援
労災で後遺障害が残った場合は、1級から14級までの等級に認定されます。
等級に応じて支給される給付額が大きく変わります。
ただし、等級の判断は医師の意見書などの書類に大きく依存し、実際の症状より低い等級が認定されるケースもあります。
労災事故に詳しい弁護士は、被害者の症状を正確に把握し、適正な認定を得るために必要な書類の内容を検討します。
また、受診方法など今後の対応についても具体的なアドバイスを行います。
もし低い等級で認定されてしまった場合も、審査請求(不服申し立ての手続き)や訴訟(裁判で争う手続き)を任せることが可能です。
【認定等級の具体例】
例えば、書類棚に右手の人差し指を強く挟み、変形や曲げにくさが残った場合は以下のような等級認定の可能性があります。
- 14級7号(指の遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの)
- 労災保険の障害補償:給付基礎日額56日分+算定基礎日額56日分+8万円(一時金)
- 慰謝料の基準:110万円
- 12級9号(一手の示指の用を廃したもの)
- 労災保険の障害補償:給付基礎日額156日分+算定基礎日額156日分+20万円(一時金)
- 慰謝料の基準:290万円
会社への損害賠償請求で交渉力を発揮できる
労災事故で会社に法的責任がある場合、労働者や家族・遺族は損害賠償を請求できます。
ただし、こうした請求はハードルが高く、当事者だけで交渉すると難航することも多いです。
もし請求が認められないと、精神的損害への慰謝料など数千万円規模の補償が全く得られないリスクもあります。
会社との対立も想定されますが、弁護士であれば高い交渉力を発揮し、より良い結果を目指せます。
法的責任を主張・立証するための専門的サポート
弁護士に相談すると、法的責任を主張・立証するための専門的サポートを受けられます。
労災事故で損害賠償請求をする際の根拠は、主に以下の2つの法的責任です。
- 安全配慮義務違反(債務不履行責任)
労働契約法第5条に基づき、使用者は労働者の生命や身体の安全を確保するよう配慮する義務があります。安全対策や教育を怠ったり、過重労働を強いた場合、会社は損害賠償責任を負います。 - 不法行為責任(民法第709条)
会社が故意や過失により労働者の権利や利益を侵害した場合に問われる責任です。業務の危険性を認識しながら十分な対策を取らなかった場合などが該当します。
例えば、高所作業中に足を滑らせて墜落し死亡したケースで、当時の安全帯が「一本つり」だったと判明した場合を考えます。令和4年2月1日施行の改正労働安全衛生法では、6.75メートルを超える作業にはフルハーネス型の使用が義務付けられており、この基準に反していれば安全配慮義務違反が認められる可能性が高くなります。
弁護士に任せることで得られる優位性
弁護士が代理人として交渉に入るだけでも、会社に大きなプレッシャーを与え、支払いの合意を引き出す力が高まります。
損害賠償請求の場面では、会社側が事故状況の認識の相違を主張したり、労働者の過失や既往症を指摘して減額を図ることがあります。
当事者だけでは、こうした主張に適切に反論できず交渉が行き詰まる場合もあります。
弁護士は、業務指示書や労働時間の記録などの客観的証拠を整理・準備し、会社の法的責任を的確に主張・立証します。
労働者の権利を保護しやすい
労災事故で療養中の労働者に対して、一部の会社は不当な扱いをするケースがあります。
たとえば、解雇や退職勧奨(会社が自主的な退職を迫ること)によって、労災補償でも不利な状況に追い込もうとする例です。
こうした対応が心配な場合でも、弁護士に相談・依頼することで、労働者の権利を適切に守ることが可能です。
労災による休業は解雇理由にならない
労災事故による休業を理由に労働者を解雇することは、法律上原則として禁止されています。
労働基準法第19条第1項では、業務災害による療養のための休業期間と、その後30日間の解雇を制限しています。
ただし、以下のような例外が法律で認められています。
- 通勤災害による休業で、職場復帰が不可能など合理的な理由がある場合
- 治療が3年を超え、傷病補償年金(長期療養で重度障害の場合に支給される年金)を受給している場合
- 治療が3年を超え、会社が平均賃金の1,200日分の打切補償(一括支払いによる補償)を支払った場合
- 天災事変などやむを得ない事情で事業継続が不可能となり、行政官庁の認定を受けた場合
これらの例外に該当するかはケースごとに判断が分かれます。不当解雇かどうかは、弁護士に相談し適切な判断を仰ぐことが大切です。
弁護士に相談することで、法律上の権利を理解し、会社との交渉を冷静かつ有利に進めやすくなります。
労災事故後の不安な状況こそ、専門家の支援を受けて自分の立場をしっかり守ることが重要です。
労災事故を弁護士に相談・依頼すると費用がかかる
労災事故の問題を弁護士に相談・依頼する場合、一定の費用がかかることは避けられません。
多くの方が「弁護士費用は高い」「自分で手続きをすれば費用を節約できる」などと考え、弁護士への依頼をためらいがちです。
しかし、実際には上記で伝えたように弁護士に相談・依頼するメリットは多くあります。
あらかじめ弁護士費用の目安を理解し、費用対効果を踏まえて判断することが大切です。
弁護士費用の相場例
弁護士費用は相談時間、依頼内容、事案の複雑さなどによって変動しますが、以下は一般的な目安です。
- 相談料:0円〜6,000円/1時間程度
※初回無料相談を設けている事務所もあります。 - 着手金:10万円〜30万円程度
※訴訟など手続きが複雑になる場合は増額されます。 - 成功報酬:得られた経済的利益の10〜20%程度
- 日当:出廷1回あたり1万円〜3万円程度
※別途、交通費や宿泊費が発生する場合もあります。 - 実費:内容証明郵便の配達料、裁判所への書類提出費用など
費用をかける価値
弁護士費用は決して小さな負担ではありません。
ただし、その分、損害賠償請求の交渉や適正な後遺障害等級認定のサポートなど、専門的で実践的な支援を受けられるのが大きなメリットです。
費用面で不安がある場合も、まずは相談料や成功報酬の仕組みを確認し、納得できる条件で依頼できる弁護士を選ぶことで安心して対応を進められます。
【関連記事】労災申請の弁護士費用はどれくらいかかる?弁護士費用特約も紹介
相談における弁護士と労働基準監督署の違い
労働問題については、各地の労働基準監督署で無料相談を受けることができます。
これはとても心強い制度ですが、注意すべき点は、労働基準監督署が「労働者の代理人」として個別の権利行使を支援するわけではないということです。
労働基準監督署は労働基準法などの法令に基づき、使用者(会社)の違反を監督し、是正指導や行政処分を行う行政機関です。
つまり、法令違反があれば是正を命じたり罰則を科したりはできますが、個別の損害賠償請求などのトラブルを代理人として解決することはできません。
損害賠償を請求する場合、権利を実際に行使する手続きは労働者本人か、正式に委任を受けた代理人が行う必要があります。
そして代理人として交渉や訴訟(裁判で争う手続き)を行えるのは、訴訟代理権と法律知識を備えた弁護士だけです。
たとえば、会社の法令違反を是正させる目的なら、まず労働基準監督署への相談が有効です。
しかし、実際に慰謝料や損害賠償などの具体的な補償を得たい場合は、弁護士への相談が重要だと理解しておきましょう。
弁護士は、法的責任を具体的に主張・立証し、会社との交渉や裁判を通じて適正な補償を得るための心強いパートナーです。
【関連記事】労災の申請を労働基準監督署にする方法|申請できる怪我や病気、受け取れる給付も解説
弁護士費用を会社に請求できる可能性がある
労災事故で会社に損害賠償責任が認められる場合、慰謝料や逸失利益(将来の収入の損失分)などの損害に加えて、弁護士費用の一部を相手に請求できる可能性があります。
これは、不法行為による損害賠償請求の判例上、必要かつ相当な範囲で弁護士費用を損害として認める考え方があるためです。
そのため、実際の負担が軽減されるケースもあります。
弁護士費用に不安を感じる方も多いですが、こうした費用負担の可能性や支払い方法については、最初の相談時に詳しく説明を受けられるのが一般的です。
費用面の不安を解消し、安心して依頼するためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
労災事故に強い弁護士の選び方
「弁護士なら誰でも労災事故に対応できる」と考えるのは注意が必要です。
実際には、弁護士ごとに経験やスキルに大きな差があり、事務所ごとの得意分野や対応姿勢も異なります。
また、相談者との相性や話を丁寧に聞いてくれるかも重要なポイントです。
適正な補償を得るために、労働者の立場に立って強力な味方になってくれる弁護士を選ぶ際は、次の点を意識しましょう。
労働者側の実績を重視して選ぶ
最低限、労災保険(労働者災害補償保険制度)の仕組みや慰謝料の相場をしっかり理解していることが必要です。
労働者側の事案を多数扱った実績があれば、交渉の進め方や会社側の主張への反論方法も豊富です。
ただし、見落としがちなのが、同じ「労働分野」の弁護士でも実績の多くが会社側の代理人としてのものというケースです。
この場合、労災保険や後遺障害等級認定に関する知識や経験が不足し、労働者側の支援に不向きなことがあります。
弁護士や事務所のホームページなどをよく確認し、「労働者側を主にサポートしているか」をしっかり見極めることが重要です。
労災保険の後遺障害等級認定に詳しい
後遺障害等級の認定は、補償額に直結する重要なポイントです。
労災に強い弁護士は、一定程度の医学的知識を持ち、医師の意見書や診断書の作成を具体的にアドバイスできます。
症状に応じた受診や検査方針まで助言してもらえるのも大きなメリットです。
相談段階から親身になってくれる
身体的な苦痛だけでなく、経済的負担や将来への不安を理解し、相談者の気持ちに寄り添う対応をしてくれる弁護士を選びましょう。
初回相談時の印象や質問への答え方も大切な判断材料です。
【関連記事】労災に強い弁護士の選び方を徹底解説!
まとめ
労災事故は、負傷や病気だけでなく、その後の生活や将来設計にも大きな影響を及ぼします。
適正な補償を受けるためには、労災保険の仕組みを正しく理解し、会社の対応や手続き上の課題を乗り越える必要があります。
ただし、手続きは複雑で、会社側が非協力的だったり、後遺障害等級認定で不利な判断が出ることも少なくありません。
こうした場面では、労災問題に詳しい弁護士に早めに相談し、専門的なアドバイスや交渉の支援を受けることが大切です。
弁護士は、適正な補償を確保するための心強い味方であり、労働者の権利を守る重要なパートナーです。
もし労災事故に遭ってしまったときは、一人で抱え込まず、ぜひ労災無料相談センターにご相談ください。